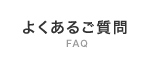紫波町図書館について
コンセプト
「知りたい」「学びたい」「遊びたい」を支援する図書館
- あらゆる「知りたい」に応え、潜在的、将来的な利用を見据えた情報を提供します。
- 「学びたい」に応え、活力あるまちづくりに役立つ情報や、町民が自力で課題解決するための情報を提供します。
また、まちの歴史・風土・文化に出合い、発信する場を提供します。 - 「遊びたい」に応え、知的好奇心を満たし、文化的、娯楽的活動などによる新しい創造と交流が生まれるための情報を提供します。
運営三本柱
- 子どもたち(0歳から高校生まで)と、本をつなぐ。
- 紫波町に関する地域資料を、収集・保存する。
- 紫波町の産業支援をする。
各種データ
| 蔵書数 | 一般書 | 70,090冊 |
|---|---|---|
| 児童書 | 36,810冊 | |
| 雑誌 | 13,201冊 | |
| 地域資料 | 11,646冊 | |
| 視聴覚資料(CD・DVDなど) | 871枚 | |
| 計 | 132,618冊 | |
| 閲覧座席数 | 一般フロア | 74席 |
| 児童フロア | 34席 | |
| 読書テラス | 18席 | |
| 学習室(交流館中スタジオ) | 30席 | |
| インターネット検索用端末 | 3台 | |
| データベース検索用端末 | 2台 | |
| 館内資料検索用端末(ほんナビ) | 3台 | |
| 自動貸出機 | 1台 | |
| 図書館延床面積 | 総面積 | 約1,574㎡ |
| (内閲覧スペース) | 約900㎡ | |
| 収蔵能力 | 開架 | 約73,000冊 |
| 閉架 | 約91,000冊 | |
| 紫波町図書館基本構想・基本計画 | PDF(2.2MB) | |
※2024年3月31日現在
5月のごあいさつ
五月に入り、新緑や田植えの風景が目に優しい季節がやってきました。年度が明けて新しい環境に慣れ始め、連休を挟んだ今のこの時期はまさに「五月病」になりやすいころ。 近年は「四月病」という言葉もあるくらい、春は環境や気象の変化にからだや心がついていくのに必死で、疲れやすい季節ですね。 毎年この時期に恒例となりつつある企画展示「-新しい季節に疲れすぎないために-人づき合いのトリセツ3」は、引き続き五月末まで開催中です。
四月からは「大阪・関西万博」がはじまり、十一月には「東京2025デフリンピック」(*国際的な「きこえない・きこえにくい人のためのオリンピック」)もあるなど、世界の国々や多文化への関心が高まっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 館内入ってすぐの児童フロアでは企画展示「せかいをみると」がはじまっています。 一般フロアでは、依然として厳しい状況が続くガザ地区のことやウクライナ情勢について、そして教皇選挙(コンクラーベ)にまつわる情報などもご用意しています。 さまざまなメディアでふれた情報から、気になる、もっと知りたい!という興味の「芽」に、お水をあげられるように。 求める情報に向かって、自ら手を伸ばしていただけるように。そんな想いでつくられている棚を、ぜひ眺めてみてください。 そしてご不明な点は、お気軽にカウンターのスタッフまでお声がけください。
5月21日(水)、22(木)からは今年度の移動図書館車「かたくり号」の運行が開始します。 およそ1500冊の本を載せて、月に2日間、町内18か所のステーションを巡回運行しています。 運行開始時から数えて4代目となり、来年には60周年を迎える「かたくり号」。 ふだん図書館までなかなか足を伸ばせないという方も、お近くのステーションがあるかどうか、運行スケジュールをご確認のうえご利用ください。
アイデアが必要なときや、考えごとをしたいとき、なんとなく寂しいとき。 本や司書が、悩みごとを聞いてくれたり、そっと新しい世界へ導いてくれるかもしれません。 気持ちがふさぎそうになるときほど、図書館のことを思い出してもらえたら嬉しいです。
令和7年5月9日
紫波町図書館長 天野 咲耶
着任のご挨拶
このたび、令和6年10月1日より新しく館長に着任しました、天野咲耶(あまのさくや)と申します。
令和3年より、SNSを中心とした図書館の広報業務に関わっておりましたが、このたび、藤尾前館長よりバトンを受け継ぎました。
改めて、簡単に自己紹介をさせていただきます。私は三年前、地域おこし協力隊に着任し、東京都中野区から紫波町へ移住してまいりました。 現在はかねてより活動していた作家業を兼業し、日詰商店街で開催する「本と商店街」など、本や文化とまちをつなぐイベントの運営にも携わっております。
振り返れば、私が東京から紫波町への移住を考えたとき、大きなきっかけとなったひとつが、この紫波町図書館でした。 入館して、「こんにちはー」と笑顔で迎えてくださったスタッフさん。 天井が高く、開放的な雰囲気の中で、うっすら流れるやさしいBGM。 棚には気になっていた本や、面白そう!と、思わず手に取りたくなるような表紙が並んでいました。
丸一日過ごしたくなり、この近所なら住める!と直感させてくれる居心地の良さがそこにはあったのです。 私がまさか館長になることは、その時には夢にも思ってみませんでしたが。
未熟な身ではありますが、いち利用者として感じていた図書館の心地よさや魅力を大切に守り、伝えていきながら、人と本、情報との出合いをさまざまな形でつないでいくことができればと思っています。
どうぞよろしくお願い致します。
令和6年10月2日
紫波町図書館長 天野 咲耶
退任のご挨拶
このたび令和6年9月30日をもちまして館長を退任することになりました。3年半という短い期間でしたが、皆様のおかげで新しい館長にバトンを渡すことができましたこと、心より感謝申し上げます。
図書館は今日もたくさんの方が訪れています。広場には自由にマルシェを楽しむ方の姿も見えます。コロナ禍を経て12年目を迎える情報交流館は、9月18日には累計400万人を達成し、図書館には年間16万人の方に来館いただいております。‛オガル’願いを込めたオガールエリアから情報を発信してまいりました図書館は、町内外の多くの皆さまで支えられてきていることを改めて感じております。
思えば20代の頃、移動図書館車かたくり号で四季折々紫波町の隅々まで巡回し、本を届けておりました。雪に埋もれる地域の公民館、緑鮮やかな田園風景、背中で泣いていた赤ちゃん。そんな光景の中で、あらためて、農作業の合間に笑顔で迎えてくれた女性たち方々の顔がはっきりよみがえってきました。
きっかけは、7月に開催された「聞き書きスト養成講座」で、かつて、生活改良普及員をされていた方のお話しからでした。「昔、農村の環境は今のようでなくて、女性の地位が低い状態が続いて、それではだめだと思って、女性たちの小さいグループで勉強会を始めたんだ。何回も集まって、一生懸命勉強したんだよ」という内容で、女性の経済的自立を目指し、食の安全を考え、農産加工物を作り、販売の方法を考え行動した結果、産直を生んだ原点へと繋がっていった様子が目に浮かびます。半世紀を経た「聞き書き」で、あの時の女性たちが、学ぶために本を手にして時代を動かしていったことを知ることができました。
そして現在、9月の企画展示では町内のコロナ禍後に開店した飲食店を紹介しており、お店のご紹介とご店主よりの紹介本が屋台のように並んでおります。利用者さんからの推薦店も日を追うごとに増え、マップもいっぱいになってまいりました。情報も少しずつ年数が重なり、町のコンシェルジュとしての役割も担えるようになっていけるとしたら嬉しい限りです。
これからも、時代を超えて人や情報が繋がり、暮らしをより豊かにする図書館として、皆さまに育てていただけますようお願いし退任のあいさつといたします。
令和6年9月29日
紫波町図書館長 藤尾 智子
4月の挨拶
昨年度も、たくさんの方々からのお力をお借りしての企画展示やトークイベントを行うことができ、町内外から多くの方にご利用いただき感謝いたします。年度も変わり、図書館も新メンバーを迎えた体制でスタートしておりますが、変わらぬご支援を頂きますようお願いいたします。
さて、今年の春も安定しない気候の中でも花が咲き散っていきます。学校や職場で、地域の中でさまざまな変化をストレスに感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな、少し不安な年度の変わり目に、人の気持ちに寄り添える展示「いつだって 大変なのは人間関係 人づき合いのトリセツ2」を開催しています。人付き合いへの心の持ち方や考え方にアプローチする本が280冊近く並んでいます。良く見ると展示している本が「貸出中」という表示になっているものが複数あります。皆さんの関心の高さがうかがえますが、同時に「同じ悩みの人がここにいる」というメッセージが、そのまま聞えてくるような気がします。
図書館では、日常会話等でご利用の皆さんが求められているものを理解することを心掛けております。ご本人の悩みや、欲しい情報を伺っているうちに、例えば「人付き合いが苦手、特に新学期」と思っている方がいるということから、様々な本や情報と寄り添い、本質的な課題を考えることで企画展示等に結びつけていきます。
人が生活する中で直面していること、介護だったり子育てだったり、ご自身の健康だったり、現実の悩みは様々ですが、人と人が共感したり共有することで本質的な社会的課題が見えてくることがあります。そんな謎ときに寄り添い、市民の皆さんとの距離を縮め、皆さん同士の緩やかな関係づくりへと進んでいけるような小さいお手伝いができたら幸いと思います。
令和6年4月26日
紫波町図書館長 藤尾 智子
6月の挨拶
新型コロナウイルス感染症の位置づけが、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。皆様の社会活動や生活にも新たな変化が感じられます。思えば、2020年4月の緊急事態宣言以来、長く閉鎖的な時間を感じられた方も多かったと思います。 活気が戻ってきたような日常、ふと目を上げると麦畑にさわやかな風が吹き、足元の草花はたくましく地に根を張り、太陽の光に向かって伸びています。長い冬の寒さが遠のき、夏の予感を感じる6月の心地良さです。人はこれまで困難を乗り越えてきた歴史の中で、自然の移ろいに自らを重ね、そのたくましさに励まされてきたのかもしれません。 図書館では、5月には児童コーナーの「草花」に関する企画展示を行いました。展示された本の表紙は、さながら草花畑にいるような植物のパワーをお届けいたしました。 6月からは、名誉町民須川長之助翁に関わる企画展示を開催しております。紫波町でも多くの死者が出たという天保の大凶作と大飢饉、その直後に生を受け、明治維新から激しく変化する時代に生涯植物採集にかけた須川長之助翁、その生きざまにフォーカスしながら地球と共に生きる植物の想いをお届けることができましたら幸いです。
令和5年6月4日
紫波町図書館長 藤尾 智子
11年目の春を迎えました
例年に無い速さで桜の季節を迎え、新しい年度を春の喜びとともにスタートいたしました。 年度末には、図書館10周年記念誌を発刊させていただきました。図書館の無かった町に図書館ができ、新しい町の顔として成長してまいりましたこと、1ページ1ページに思いをはせながら編集いたしました。改めて共に歩んでいただきました皆様に感謝申し上げ、新しい10年に向かって歩み始めます。 現在図書館では、一般企画展示「人づき合いのトリセツ―『はじめまして』が不安なあなたへ―」を開催中ですが、大変好評で展示図書に「貸出中」が続出しております。何かが変わり、素敵なことに出会える春、図書館はそんな皆さんの応援団です。
令和5年4月15日
紫波町図書館長 藤尾 智子
10周年にあたって
紫波町図書館は2012年8月31日に誕生し、10周年を迎えることとなりました。 図書館ができるまでの間、図書館に代わる施設として活躍してきた胡堂文庫(紫波町中央公民館図書室)。小さな体にランドセルを背負い、学校帰りの子どもたちであふれる公民館の一部屋。四季折々の風景の中、本届ける移動図書館車。皆さんの本棚を見上げる姿と本に対する愛情は半世紀たってもかわりません。 そんな皆さんの願いを受けてスタートした紫波町図書館。 10年間で登録者数が2万人を超え、貸出総数約220万冊、入館者総数約184万人と当初の予想をはるかに上回るご利用をいただいております。 そして、ご利用いただいたみな様の数だけドラマが聞こえます。 「本棚で迷っていたら、即座に探していた本を差し出してくれました。」「地図では分からなかった町内の場所にたどり着くことができたのです。」「産直で初めて見た野菜がレシピ本の紹介で新しい味との出会いになりました。」「『出張としょかん』で農業情報が身近になり、若い人へ農業を継ごうという想いになりました」「懐かしい本に出合えて自分をふりかえるきっかけができました」などなど。そして、「図書館は人ですね」とおっしゃっていただいたことも私どもの大きな励みとなっております。 これからも人と情報をつなぐ役割を担う図書館として、職員一同、皆さんと共に工夫と挑戦を重ねてまいりたいと存じます。
令和4年8月31日
紫波町図書館長 藤尾 智子
新年にあたって
新年あけましておめでとうございます。 新年をすべての新しい始まりとしてとらえた日本の習慣をことさら美しいと感じた2022年のスタートでした。昨年は、若い方の活躍など明るいニュースも多くありましたが、全体が新型コロナウィルスという見えない恐怖や世の中のあり方の急激な変化といった不安な気持ちが漂っていたように思います。 そういった状況をふまえて、当館では、図書ばかりでない生きた情報をお届けするよう心掛け、心に届く日常へと思いをはせて企画させていただきました。 今年度は、8月31日に開館から10周年を迎えます。これまでの軌跡をふりかえり、これからのあり方を模索する年として気を引き締め、 皆さまに愛される図書館を心がけてまいります。 重層的な時の流れの中で10年の節目が小さくてもひとつの輝きがあるものとなっていけたらうれしいと感じております。
令和4年1月4日
紫波町図書館長 藤尾 智子
9周年にあたって
紫波町図書館は、おかげさまで8月末日、開館から丸9年を迎えました。 思えば、9年前には、東日本大震災後の混乱が続く中での開館。 手探りながら、様々な挑戦を続け、2016年には、ライブラリー・オブ・ザ・イヤーの優秀賞を受賞するなど、町内外から注目される施設に成長できました。 これも、大切にしていただき、応援してくださった皆様あってのことと深く感謝申し上げます。
現在、思いもよらない新型コロナウィルス感染症の拡大の中で、皆様が自分のための本、人、情報との出合いができるよう、町の方針に沿った感染防止に留意しながら開館しております。
館内には、いつも身近にある、鳥や虫、草花、星や石など自然にスポットをあて、それぞれの達人たちに、紹介いただいた本や写真を展示してあります。このコーナーを見た子どもが、実物に出会うため外に出かけていきます。知っている動植物の名前を見つけて、ご自分の体験を話してくださる方がいます。困難な時ではありますが、本という情報にとらわれず、新しい人や出来事、情報に出合う場としてご活用いただけましたら幸いに存じます。
私こと4月1日に館長に就任いたしました。これまでの積み重ねを大事にしながら、職員とともに皆さんご自身の「知りたい」「学びたい」「遊びたい」をさらに応援できる図書館であり続けたいと存じます。
令和3年8月31日
紫波町図書館長 藤尾 智子
退任のご挨拶
この度、令和二年三月末日をもちまして、館長を退任することになりました。
図書館も館長も全くゼロからのスタートでしたが、町民、利用者の皆様からのご支援と、司書の努力による図書館サービスの構築と展開により、ここまで来ることができました。心から感謝申し上げます。
開館当初から、目標を大きく上回る利用者がありました。いかに図書館が待ち望まれていたかが分かりました。それに加えて、ユニークな企画展示・イベントの取り組みや、従来の図書館の枠を超えたサービス展開が、利用者の幅を広げることにつながっていきました。
また、ライブラリーオブザイヤー優秀賞、調べる学習コンクール文部科学大臣賞そしてアメリカ図書館協会ジャパンセッションに初参加と、想像もしていない嬉しい出来事がありました。
退任を迎えた今、初めて館長辞令を頂戴した時、元町長から「日本一の図書館になれ」と言われたことを思い出します。とてもそのミッションは達成できたとは思われません。高い評価を獲得できたとも思ってはいません。評価は町民・利用者が行うものです。
しかし、次のランナーにバトンを渡すことができるバトンゾーンまでは、転ばずに何とか走りきれたと思っています。
「シハ」(アイヌ語が語源)とは鮭が昇る川の意味らしい。そのシハ(山王海)から一千五百万年前の鮭の化石が発掘されています。日本列島が形成される以前から鮭は紫波のあたりで生を繋いでいました。
鮭にとってシハには良い何かがあったのでしょうか?いま、紫波には図書館があります。良い図書館に育てて欲しい。沢山の鮭が昇り、生を育む。その様な夢を次代に託します。
図書館の利用者の皆様、そして将来の利用者の皆様に、心から御礼申し上げます。
令和2年3月31日
工藤 巧
5周年にあたって
紫波町図書館は、町初めての図書館法に基づく図書館として、本年8月末日、開館5周年を迎えることができました。胡堂文庫によって種を蒔かれた読書の喜びが、五十年の月日を経て、ようやく、しかし、確実に花を開きました。
本格的図書館が欲しいとの町民の声が高まり、「紫波町公民連携基本計画」に待望の図書館建設が位置付けられてから十年経過いたしました。未曾有の三陸大震災の直後、着工が危ぶまれながら英断を持って着手し、翌年竣工いたしました。 それ以来利用者は、「紫波町図書館基本構想・基本計画」において目標とされた入館者数を大きく上回り、一定の成果を達成できたものと考えております。「紫波町公民連携基本計画」の計画時点においては、図書館の利用に対する懐疑的な意見もありましたが、 開館後におきましては多数の賛辞が寄せらせており、多くの町民・利用者が図書館の開館を待ち望んでいたことがうかがわれます。「図書館ができて良かった!」の声は、図書館職員にとって何よりの喜びであります。 その様な声を聴くたび、より一層図書館サービスの向上に努めなければと力が入ります。
これまでの5年間は、初めて町にできた本格的な図書館であるため「できることは何でもしよう」の猪突猛進的な精神で取り組んでまいりました。「初心者に怖いもの無し」でしたが、振り返ってみれば大過なく運営できたのではないでしょうか。結果オーライです。
選りすぐりの本、貸出と返却、検索システム(館内OPAC)、自動貸出機、ICタグ、減震書架、飲食可の読書テラス、WiFiフリー、貸出15日間、一般・児童企画展示、おはなし会、サイエンスおはなし会、マルシェのPOP、調べる学習コンクール、夜のとしょかん、出張としょかん、こんびりカフェ、連携イベント等々・・・
なかでも、「ただようまなびや文学の学校岩手分校」(2014.10開催)は、図書館サービスが大きく広がるきっかけとなりました。ワークショップに町内外からたくさんの参加がありました。またこれを機会に、出版社や著名な方々との出会いがあり、PRをさせていただきました。 お陰様で、その後、いろいろな方々との出会いが増え、図書館の枠を超えてサービスを展開するようになりました。この場を借りて、関係したすべての方々に、心から感謝申し上げます。同時に、充分な環境とは言えない中で、ライブラリー・オブ・ザ・イヤー2016優秀賞を 受賞するまでに図書館業務を支えてくれた司書を誇りに思います。
オガールの施設が全て完成し、これからがオガールの本番であります。次の5年間は、開花から結実の期間であります。図書館が「あってよかった」から「なくてはならない」情報の拠点へと成長し、紫波のまちづくりを支えてまいります。今までの経験を踏まえて明確な理念を持ち、 計画を立て、図書館の本来の使命を果たすサービスの展開を目指してまいります。
何かあったら図書館へ!何が無くても図書館へ! 図書館は皆様とともにあります。
平成29年8月31日
紫波町情報交流館館長
紫波町図書館館長
工藤 巧
4周年にあたって
紫波町図書館は、本年8月末日をもちまして、満4周年となりました。この間、町内外からたくさんの入館者があり、累計で82万人以上、情報交流館全体では141万人以上の人々にご利用いただきました。ご利用者の皆様方からは、「明るくて素敵な図書館ですね」とか「選書が素晴らしいです」とか「司書の対応が温かく感じがよいですね」などと身に余る賛辞も頂戴し、職員の励みとなりました。 開館当初は、初めての本格的図書館であり、誰も経験がなかったため、混乱した対応でご迷惑をおかけした場面も多々あり、また、お叱りも受けました。しかしながら、私たちはそれを図書館を良くしたいという天の声だと捉え、ひとつひとつ解決に向けて努力してまいりました。どのような些細なことも、対面で会話をすることに全力を注いでまいりました。ネットやメールが発展する時代であるからこそ、生のコミュニケーションを大切にしていきたいと、ご利用者への声掛けと挨拶に注意を払ってきました。この様な取り組みに対しまして、ご利用者の皆様方も、温かく応対していただきました。ここに、心より感謝申し上げます。
4年の間には、県内外からたくさんの視察・見学者がありました。オガールというまちづくりの中核施設としての図書館が、地方創生の政策とも相まって関心を持たれたようです。平成26年9月には、小泉進次郎地方創生担当政務官(当時)のご来館があり、視察者の増加に拍車を掛けました。またその年の秋、NHKおはよう日本では農業支援サービスが紹介され、産直マルシェのメニュー本ポップが、全国に放映されました。更に、来館者が増えることとなりました。初めて取り組んだ「調べる学習コンクール」では、森田開君が文部科学大臣賞を受賞する快挙となりました。 この様な取り組みが評価されて、2016ライブラリーオブザイヤーの優秀賞4館に選ばれました。
図書館の運営は、基本サービス(貸出、レファレンスなど)の充実はもちろんのこと、次の三本柱を中心に展開してきました。 一 子どもたち(0歳から高校生まで)と、本をつなぐ。 二 紫波町に関する地域資料を、収集・保存する。 三 紫波町の産業支援をする。 一の児童サービスは、図書館の基本であると言えます。貸し出しに占める児童書の割合は50%を超えており、今後も図書の充実を図ってまいります。また、「調べる学習」のように子どもたちの多面的な能力の発達に寄与するサービスに取り組みます。ニの地域資料については、各種地域の記録と記憶を残すことであり、東日本大震災でその重要性が認識されているところです。地域に生きてきた証を大切にしていきたいと思います。三については、紫波町の基盤である農業の支援を中心に、生産者、流通、消費者のサイクルが繋がるよう展開してしてまいります。これらに加えて、今後は、生活情報支援やハンディキャップサービスに取り組み、より役に立つサービスの展開に努めてまいります。
紫波町図書館の基本姿勢は、常に図書館の外を意識し、他者と連携を図り、情報を発信していくことです。そのことにより、連携した人々や組織またその周辺の人々まで、図書館が広がったと解釈します。広がることにより、生活の基盤としての役割を果たすことができます。図書館は、このようにしてオガールエリアから町全域、やがては町外へと広がっていきます。紫波町30km圏をターゲットとしたオガールプロジェクトですが、いずれはその枠も飛び超えたいと考えております。
入り口を入ると、子どもたちの賑やかすぎる声が元気を与えてくれます。更に進むと吹き抜けの下に、企画展示の本と共に、そのテーマにあった展示物が目に飛び込んできます。今日はどの本にしようか?迷っていると、柔らかに耳に届くBGMにつられて、思わず本に手が伸びます。それでも迷ったなら、迷わずレファレンスへ。
何かあったら図書館へ、何が無くても図書館へ!!おでってくなんせ!!
平成28年8月31日
紫波町情報交流館館長
紫波町図書館館長
工藤 巧
館長あいさつ
町民待望の本格的図書館が開館いたしました。野村胡堂生誕130年である本年、胡堂文庫から紫波町図書館へと知のバトンタッチが行われますことは、誠に感慨深いものがあります。
胡堂文庫は、野村胡堂から贈られた基金により昭和38年に設置され、町民に長く愛され利用されてきました。巡回図書館車も設置し、ボランティアグループの活動なども盛んに行われるようになり、町民の読書要望に対して少なからぬ貢献をしてきたところであります。しかし、紫波中央公民館の一室では利用者の増加に対応できなく、事業活動も限定され、また蔵書数にも限界があるため、早くから独立した図書館の建設が望まれておりました。昭和58年、町制要覧に独立図書館の建設が記載されて以降、生涯学習センター構想、総合インテリジェントセンター構想と名を変えながら、平成13年には紫波町総合計画に生涯学習センター施設整備が計上されましたが、諸般の事情により容易に建設できないでおりました。
その間に、町民の図書館に対する熱意は次第に高まり、「図書館を考える会」に始まる町民の地道な活動と、図書館が紫波中央駅前「オガールプロジェクト」の重要施設と位置付けられたことにより、胡堂文庫から半世紀を経てようやく実現の運びとなりました。
本年はまた、胡堂が生涯の先生と仰ぐ新渡戸稲造生誕150年の年でもあります。稲造は、胡堂が旧制一校時代の校長であり、後に国際連盟事務次長に就任した国際人であります。事務次長時代に始めた国際知的協力委員会は、第二次大戦後ユネスコへと発展し、昨年パリで開かれたユネスコ・世界遺産委員会において平泉が世界歴史遺産に登録されたことは、平泉と関連の深い紫波町にとっても意義深く、何らかの縁を感じざるを得ません。
偉大な先達の記念すべき年に、紫波町図書館が開館できますことは、あたかもお二人から祝福されているようであり、大きな喜びであるとともに、震災後混迷を深める現在において、何かしらの示唆を与えていただいいているように感じております。浅学の私には、それが何なのか未だ不明ではありますが、願わくば皆様と共に探してみたいものだと思っております。
木目の見える柱や梁がむきだしの図書館に入ると、木のこどもである本に囲まれて、まさに森林浴を浴びているような爽やかな気持ちになります。ぜひ皆様にも感じていただきたいと思います。私たち職員一同は、皆様に快適にご利用していただけるよう、誠心誠意努力をいたしてまいります。
皆様のご来館を心からお待ちいたしております。
平成24年8月31日
紫波町情報交流館館長
紫波町図書館館長
工藤 巧